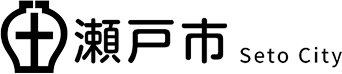障害者差別解消法について
更新日:2025年4月1日
ID番号: 1516
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日から施行されました。
障害者差別解消法のポイント
この法律では、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)に対して、差別の解消に向けた具体的な取組みとして、「障害を理由とする差別」の禁止を求めています。
「障がいを理由とする差別」には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
行政機関では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。
民間事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の不提供」は努力義務(提供に努めることは義務付けられるが、提供義務までは求められない)となります。
なお、事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論はこの法律の対象外となっています。
◎この法律で守らなければならないこと
| 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
|---|---|---|
| 国の行政機関・地方公共団体等 |
【禁止】
|
【法的義務】 障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮を行わなければなりません。 |
| 民間事業者(民間事業者には、個人事業者のほか、社会福祉法人、NPOなどの非営利事業者も含みます。) |
【禁止】
|
【努力義務】 障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
この法律の対象者とは
障害者差別解消法の対象となる「障害者」は、いわゆる「障害者手帳」の所持者に限定されるものではありません。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害や社会的障壁によって継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方すべてが、この法律の対象となります。
不当な差別的取扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、障害があることのみを理由に、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけない条件をつけたりすることです。
例えば、次のような場面が考えられます。
- レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
- スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
- アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
実際の場面において「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
障害者への合理的配慮とは?
「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
例えば、次のような場面が考えられます。
- 車いすの人が、役所職員に高い場所の書類を取って欲しいと依頼したのに放置された。
- 視覚障がいのある人が、レストランでメニューの読み上げを依頼したが読んでもらえなかった。
- 聴覚障がいのある人が、窓口で筆談を申し入れたが対応してもらえなかった。
実際の場面において「合理的配慮の不提供」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)
障害者差別解消法の関連情報
関連資料
関連リンク